『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』(山口周 著)は、悩めるリーダーへの一冊です。本書を読み、自分自身のマネジメントをふりかえるきっかけになりました。
- 私は5人チーム(ベテラン2名、中堅1名、若手1名+自分)のリーダー
- 最近チームとして「うまく回っていない」と感じている
- 業務量は100%を超えており、余白も視野も持ちづらい状況
そんな状況で本書を手に取り、書かれていた内容を自分の実情に照らし合わせながら読み進めたところ、「今の自分に必要な視点」がいくつも見えてきました。
この記事は、私自身のふりかえりの意味も込めて、学びと実感、そしてこれから実践したいことを整理した記録です。
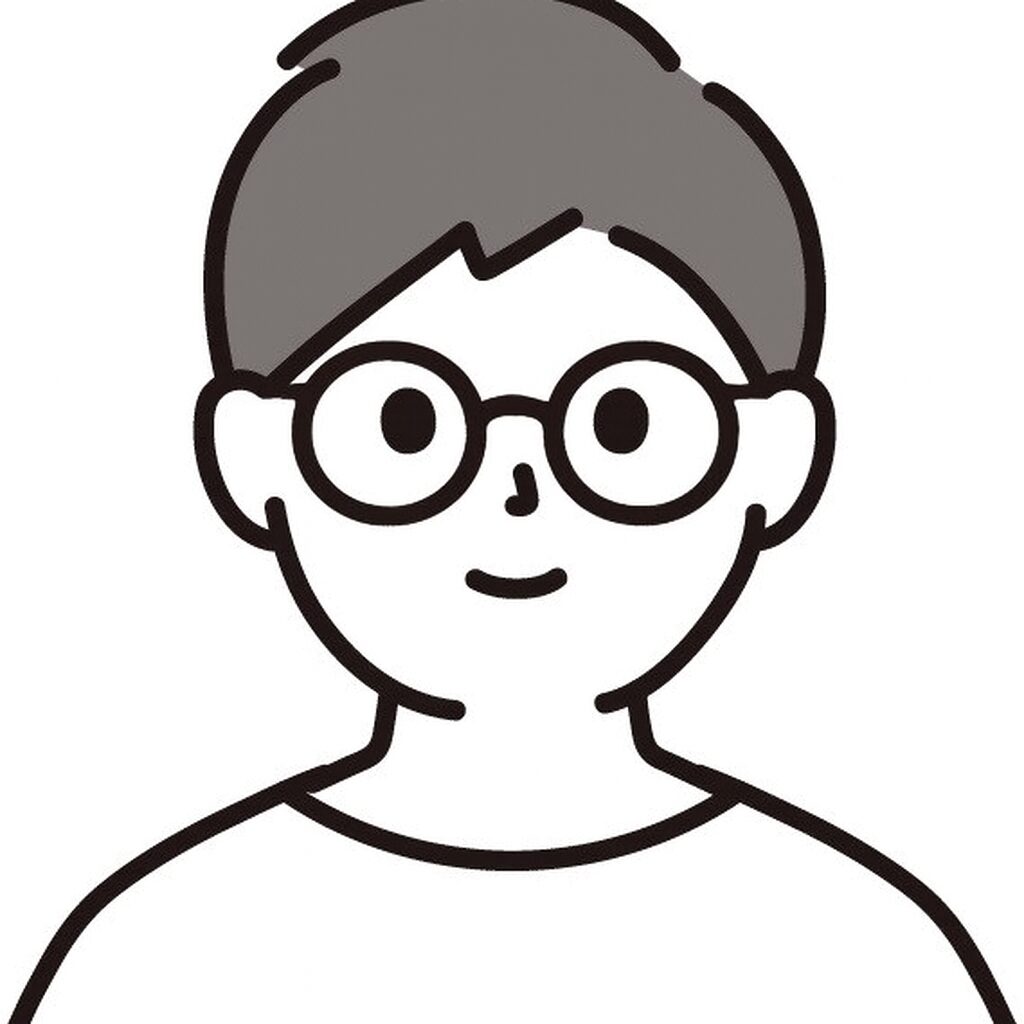
同じように悩みながらチームを引っ張っている方にとって、何かのヒントになれば幸いです。
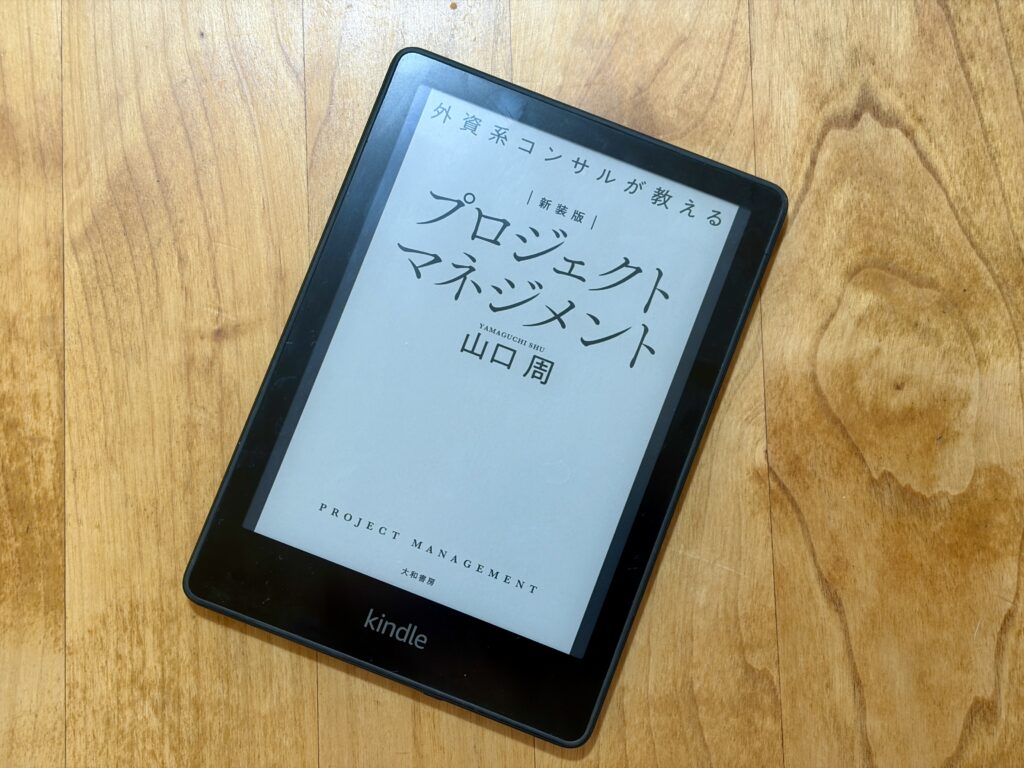
- チームマネジメントがうまくいかず悩んでいるリーダー
- メンバーのリソースや成長をどう設計すべきか迷っている
- 情報共有や報告の仕組みを見直したいプロジェクトマネージャー
- 書籍『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』の要点と現場での活かし方を知りたい
- 書籍で紹介されているリーダーのリソース配分やチーム設計の考え方
- 情報共有の「構造化」や報告の観点の転換
- チームの心理的安全性や主体性を高めるための具体的手法
- 実際のプロジェクト現場で感じた「理論と現実のギャップ」とその向き合い方
チーム運営で見直したいマネジメント視点

想定外に備える「リソース70%運用」
プロジェクトのリソースは70%稼働程度が理想 (100%ギリギリはNG)。プロジェクトには必ず想定外の出来事が起こり、余裕のない体制ではすぐに破綻してしまう。
理屈としては納得していましたが、改めて文字で読んで“今の自分に欠けている視点”だと感じました。私のチームもフル稼働状態で、日々ひやひやしています。余白がないと、判断力も落ち、負のループが生まれる。持続可能な運営には、余力(バッファ)が不可欠だと痛感しています。
先日、マネージャーに「私は突発業務やメンバーのフォローにまわるため、自分のタスクを100%埋めずにバッファを持たせたい」と伝えたところ、「そんな余裕はない」と一蹴されてしまいました……。
ただ、私の狙いは“私一人がどれだけ動けるか”ではありません。私の稼働を少し減らした分で、
- チーム全体のボトルネックを潰す
- タスク進行の遅れを早期に察知する
を実現し、チームのアウトプット総量が上げることでした。
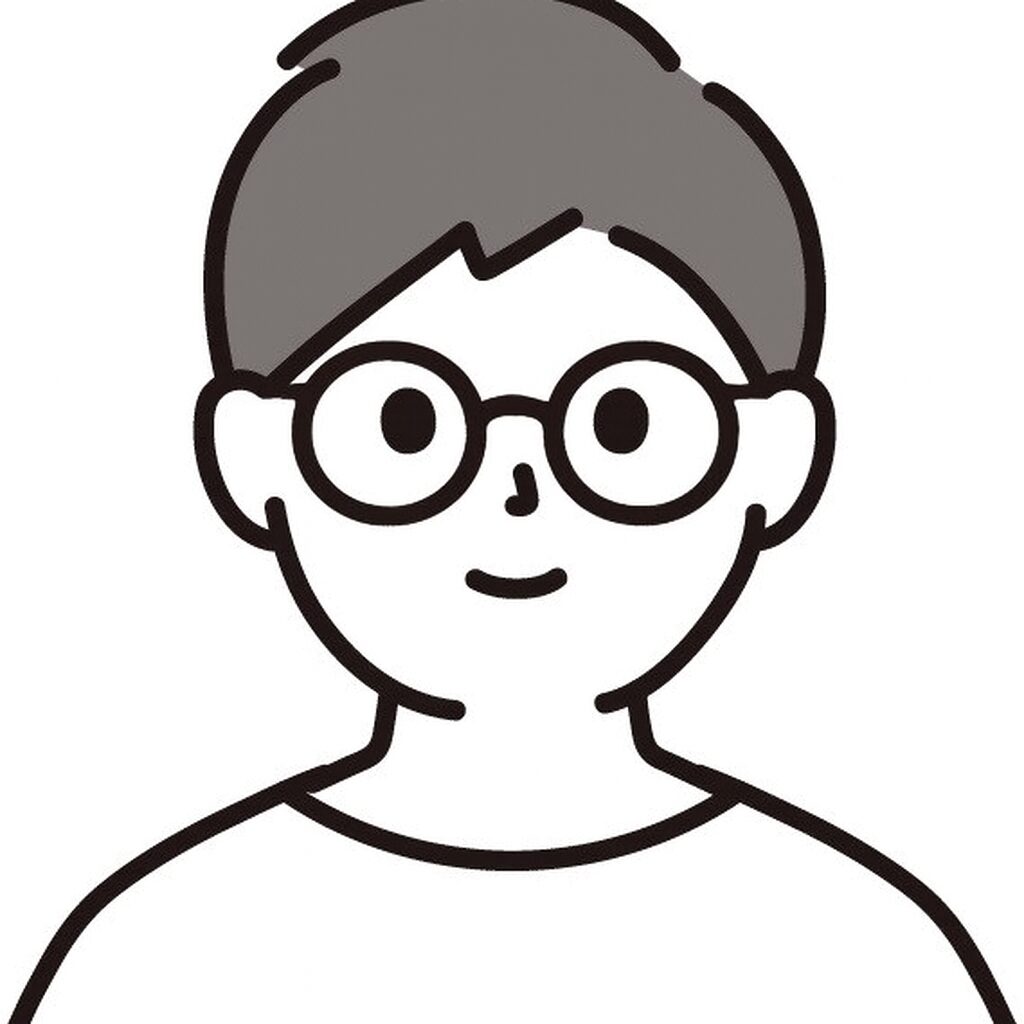
この視点を理解してもらうには、定量的な結果と継続的な信頼の積み重ねが必要だと感じています。
成長を見越したアサイン設計
「簡単なタスクは優秀な人に任せて忘れる」
「難しいタスクは育成対象に任せ、マネージャー(リーダー)がサポートする」
これは正直、目から鱗の考え方でした。育成を意識したアサインという意味では理にかなっていると思います。これまでは“できる人に頼る”癖がついていました。
すぐに実践するのは難しいですが、「あえて任せて育てる」という目線は意識していきたいです。
意思決定を止めないキーマン管理
「プロジェクト開始時にキーパーソンの予定を3ヶ月先まで月1で押さえておく」
シンプルながらとても実用的。意思決定の遅れはプロジェクトの停滞に直結するので、先手の管理が重要です。
思い返せば、私も過去に「捕まらない問題」で何度も停滞を経験してきました。事前に押さえる意識を持って動いてみようと思います。
情報の流れを設計する
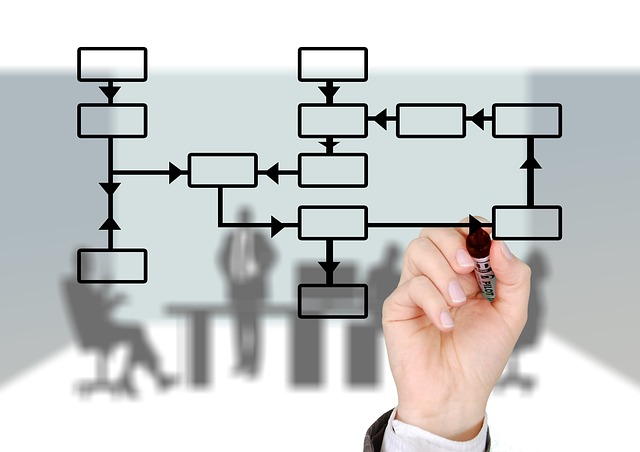
情報共有は「構造化」して流す
チーム内の情報流通量がプロジェクトの健全性を決める。共有が滞ると、問題は顕在化せずに拡大する危険性がある。
情報共有を“習慣”に頼るのではなく、“構造”で保障すべきというメッセージに納得しました。
私は「調査→検証→まとめ→共有」の型をチームに根付かせようとしています。
さらに、JIRAのコメントをREST API+Pythonスクリプトで自動収集し、AIで要約する取り組みを始めました。これにより、チケットを1件ずつ開く手間が省け、報告効率が格段に上がる見込みです。
ノエル先生のざっくり解説コーナー
~JIRA / REST API / Python~
JIRA

ソフトウェア開発や業務タスクの進行状況を管理できるツール。チケット(課題)ごとに担当者・期限・ステータスなどを記録しておけるため、複数人のチームでもタスクの見通しを保ちやすいぜ!
REST API+Python

Rest APIは、今回のケースだとJIRAに外部からアクセスして情報を取得・操作できる仕組みのひとつだぜ!Python(プログラミング言語)を使えば、JIRAに書き込まれたコメントを自動で集めたりすることもできるぜ!
フィードバックは「人格」ではなく「行動」に向けて
フィードバックは“being(人格)”ではなく、“doing(行動)”に対して行うべし。人格への評価は防衛的反応を引き起こすだけ。
自分の中でも“良かれと思って”の言葉が、実は逆効果だったかもしれないと感じました。相手の変化を促したいときほど、事実と行動に即して言葉を選ぶ。この姿勢を徹底したいです。
報告は「進捗」より「洞察と次の一手」
「何をやったか」よりも「何がわかったか」「それに基づいてどう動くか」が重要。
言われてみれば当然なのに、実際には“作業の羅列”になりがちでした。「詰まってるときこそ報告しにくい」と感じてしまいますが、そういうときにこそ“仮でも今の結論”を言葉にして共有していくことが大事だと思いました。
チームの空気と心理的安全性を育てる

目的と期待を言語化して伝える
「かけがえのない役割」を担っていると実感できるとき、最も高い充実感と責任感を持つ。
目的・背景・役割を“明文化”して伝えることは、自己効力感を高めるうえでも重要。私は業務依頼時に「なぜそれをお願いするか」は伝えるよう心がけていますが、権限委譲はまだ不十分。任せきる勇気とサポートのバランスを模索中です。
チーム憲章で安心と主体性を両立させる
「すべての意見を歓迎する」「絶対に否定しない」などの原則を明文化した“チーム憲章”を、メンバーとともにつくるべし。
心理的安全性を“空気”に頼るのではなく、“言語”で設計する。このアプローチに深く共感しました。これは今後のチーム運営でぜひ取り入れたい施策。まずはドラフトを用意して、対話のきっかけにしたいと思います。
最初に話す人が「場」をつくる
集団の中で最初に話し始める人は、「知的でリーダーシップがある」と見なされる (バイアス)
私は無意識に最初に話すことが多かったのですが、これを“戦略的に使う”意識を今後は持っていきたいです。
ステークホルダーの「裏マップ」を可視化する
関係者を「影響力×スタンス」でマッピングする“裏マップ”を活用することで、利害関係の構造が見える。
これまで“感覚”でやっていたことを構造化するための有効な手法だと感じました。今後のプロジェクトで早速試してみたいと思います。関係構築や根回しの戦略が変わりそうです。
まとめ:悩めるリーダーへ…今の自分に足りない視点がわかる1冊

本書を読んで見えてきたのは、「今の自分に足りない視点」でした。
- 今の体制は持続可能か?
- 情報は本当にチーム内で流れているか?
- 育成と成果のバランスは取れているか?
こうした問いを自分に投げかける時間が、マネジメントの質を高める一歩になると実感しています。この記事は、そんな私のふりかえりの記録でもあります。
悩みながら進む誰かの背中を、少しでも後押しできる内容になっているとうれしいです。
本書には、今回紹介しきれなかったたくさんの学びがあります。気になる方は、ぜひ『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』を手に取ってみてください。
悩めるリーダーにとって、具体と抽象を行き来する思考も大切です。
それでは今回はここまで。少しでもお役に立てたらうれしいです。
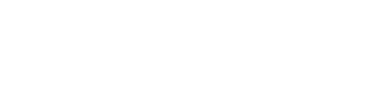
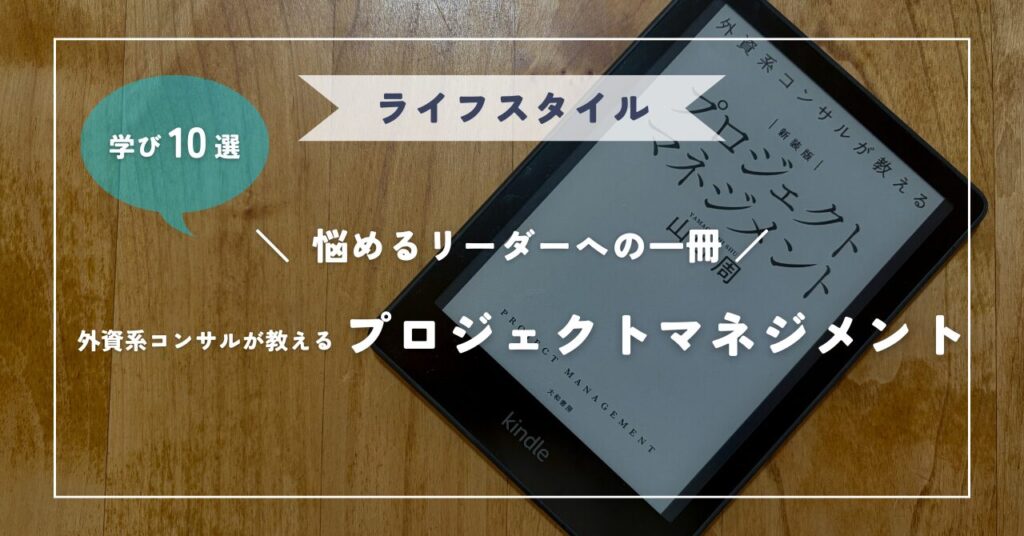


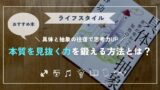





コメント